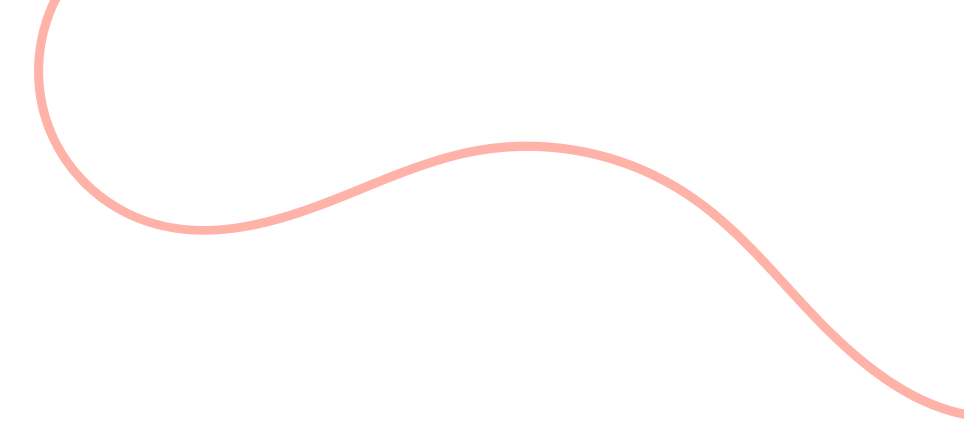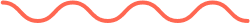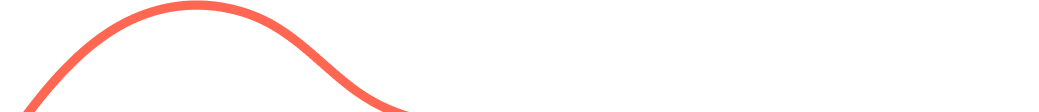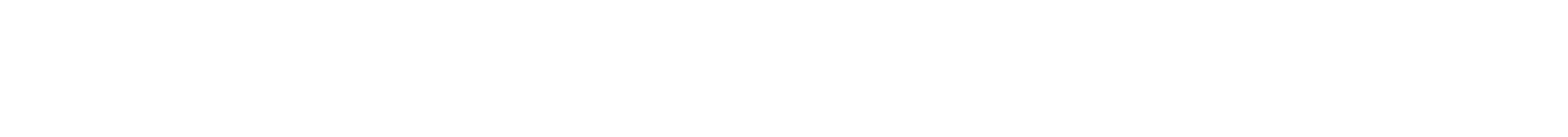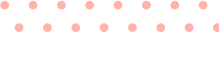電池が電気を生む基本の仕組み
電池は、化学反応によって電気を生み出す装置です。
私たちの身の回りにある機器の多くは、電池から供給される電気で動いています。
電池が電気を作り出せるのは、内部に特定の材料が組み合わさり、それらの間で化学反応が起きるためです。
プラス極とマイナス極という2つの異なる金属と、その間を満たす電解液が揃うことで、電子が一定方向に流れ続け、安定した電流が生まれます。
この電流が、光や音、動力といった様々な働きを作り出すのです。
電池を構成する3つの要素
電池は、プラス極、マイナス極、電解液という3つの基本要素から構成されます。
プラス極には銅や二酸化マンガンなどが使われ、マイナス極には亜鉛やカーボンといった異なる性質の金属や材料が用いられます。
この2つの極は直接接触していませんが、電解液という特殊な液体に浸されています。
電解液には希硫酸や水酸化カリウムなどが使われ、イオンを通す性質を持ちます。
この3つが組み合わさることで初めて、電池として機能する条件が整うのです。
どれか1つでも欠けると電気は生まれず、また材料の組み合わせによって電池の電圧や性能が大きく変わります。
身近な乾電池も、この基本構造に基づいて作られています。
電子の流れが電気になる原理
電池内部では、マイナス極から放出された電子が導線を通ってプラス極へ移動し続けることで電流が発生します。
具体的には、マイナス極の亜鉛が電解液に溶け出す際に電子を残し、この電子が外部の回路を通ってプラス極へ流れていきます。
電子の移動と逆方向に電流が流れる仕組みとなっており、この電流が機器を動かす力となるのです。
電池の電圧は、使用する材料の組み合わせで決まります。
例えば、マンガン乾電池やアルカリ乾電池は1.5V、リチウムイオン電池は3.7Vといった具合に、プラス極とマイナス極の材料によって電圧が異なります。
電池がなくなるということは、この化学反応に必要な材料が使い果たされ、電子の流れが止まることを意味します。
電池の中で起きる化学反応
電池が電気を作り出す過程では、目に見えない化学反応が連続して起きています。
この反応は、プラス極とマイナス極で同時に進行し、互いに影響し合いながら電流を生み出します。
マイナス極では酸化反応、プラス極では還元反応と呼ばれる正反対の化学変化が起こり、この2つの反応がバランスを保つことで安定した電気が供給されるのです。
電解液は、これらの反応をつなぐ重要な役割を担っています。
マイナス極で起きる酸化反応
マイナス極では、金属が電解液に溶け出しながら電子を放出する酸化反応が進みます。
亜鉛を使った電池を例にすると、亜鉛原子が電子を残したまま亜鉛イオンとなって電解液の中に溶けていきます。
この時、残された電子がマイナス極に蓄積され、導線を通ってプラス極へ移動しようとする力が生まれます。
亜鉛が溶ける量に応じて電子の数が増えていくため、連続的に電流を流すことができるのです。
金属がイオンになりやすい性質を持つほど、より多くの電子が放出され、電池の性能が高まります。
マイナス極に使われる材料によって、電池の種類や特性が決まります。
マンガン乾電池やアルカリ乾電池では亜鉛が、リチウムイオン電池ではカーボン系の材料がマイナス極として使われています。
プラス極で起きる還元反応
プラス極では、マイナス極から移動してきた電子を受け取る還元反応が起こります。
ボルタ電池の例では、電解液中の水素イオンが銅板に到達した電子と結びつき、水素ガスに変化します。
この反応によって電子が消費されるため、マイナス極から新たに電子が供給され続け、電流が途切れることなく流れ続けます。
プラス極の材料には、電子を受け取りやすい物質が選ばれます。
マンガン乾電池では二酸化マンガン、アルカリ乾電池でも二酸化マンガン、リチウムイオン電池ではコバルトやニッケルなどの金属酸化物が使われています。
プラス極とマイナス極で同時に反応が進むことで、電池は安定して電気を作り出せるのです。
一次電池と二次電池の違い
電池は大きく分けて、使い切りタイプの一次電池と、充電して繰り返し使える二次電池の2種類があります。
一次電池は化学反応が一方向にしか進まないため、材料が使い果たされると使えなくなります。
一方、二次電池は外部から電気を与えることで、放電時とは逆向きの化学反応を起こし、材料を元の状態に戻すことができます。
そのため何度も充電して使い続けられるのです。
用途や使用頻度に応じて、適切なタイプを選ぶことが大切です。
使い切りタイプの一次電池
一次電池は、内部の材料が化学変化を終えると使えなくなる使い切りの電池です。
代表的なものに、マンガン乾電池とアルカリ乾電池があります。
マンガン乾電池は公称電圧1.5Vで、安価で手に入りやすいのが特徴です。
時計やリモコンなど、小さな電流で動く機器に適しており、休ませると回復する性質があるため、時々使う懐中電灯などに向いています。
アルカリ乾電池も公称電圧1.5Vですが、マンガン乾電池より大容量で電圧の低下が少なく、液漏れしにくい構造になっています。
そのため、デジタルカメラやラジカセなど、大きな電流を連続して必要とする機器におすすめです。
リチウム一次電池は公称電圧3.0Vと高く、容積あたりのエネルギー量はマンガン乾電池の最高10倍にもなる高性能な電池です。
繰り返し使える二次電池
二次電池は、充電することで材料が元に戻り、何度でも使える電池です。
ニッケル水素電池とリチウムイオン電池が代表例で、スマートフォンやノートパソコンなど多くの電子機器に使われています。
ニッケル水素電池は公称電圧1.2Vで、ニカド電池と同じく充電して繰り返し使えますが、より高容量で持続時間はニカドの約1.5から2倍です。
デジタルカメラなど長時間使いたい機器に適しています。
リチウムイオン電池は公称電圧3.7Vと高く、他の二次電池に比べて軽量で大容量、自己放電率が少なく、メモリー効果も起きない優れた特性を持ちます。
1990年代に登場した新しい電池で、現代の電子機器には欠かせない存在となっています。
充電時に起きる逆反応
充電は、放電時とは逆向きの化学反応を起こすことで電池を元の状態に戻す仕組みです。
リチウムイオン電池を例にすると、放電時にはマイナス極から正極へリチウムイオンが移動しますが、充電時は電源から電流を流すことで、正極からマイナス極へとリチウムイオンが戻っていきます。
正極では電子とリチウムイオンが放出され、マイナス極では移動してきたリチウムイオンが電子を受け取って蓄えられるのです。
こうして、使い終わった電池が再び放電できる状態に戻ります。
ただし、充電と放電を繰り返すうちに材料が少しずつ劣化するため、二次電池にも寿命があります。
身の回りの電池の種類
私たちの周りには、用途や機器に合わせて開発された様々な種類の電池があります。
円筒形の乾電池から薄型のボタン電池、スマートフォンに内蔵されたリチウムイオン電池まで、それぞれ異なる特徴と適した使い道があります。
形状や材料、電圧の違いによって、時計のように微弱な電流で長時間動くものから、電動工具のように大きな電力を必要とするものまで、幅広い機器に対応できるのです。
乾電池の仕組みと用途
乾電池は、最も身近で広く使われている一次電池です。
マンガン乾電池は、マイナス極が缶容器を兼ねた構造で、安価で手に入りやすいのが特徴ですが、スイッチの切り忘れなどで過放電すると缶に穴があいて液漏れすることがあるため注意が必要です。
懐中電灯など時々使うものや、短時間繰り返し使うものに適しています。
アルカリ乾電池は、外装缶が化学反応に関係しない構造のため液漏れしにくく、マンガン乾電池よりも大容量で電圧低下が少ないのが利点です。
そのため、強力ライトなど大きな電流で使うものや、ラジカセなど連続して使う機器におすすめです。
どちらも公称電圧は1.5Vで、形状やサイズは同じですが、性能と適した用途が異なります。
リチウムイオン電池の特徴
リチウムイオン電池は、正極と負極の間をリチウムイオンが移動することで充放電を行う二次電池です。
正極にはリチウムを含む金属酸化物、負極には黒鉛などのカーボン系材料が使われ、その間をリチウムイオンが電解液を通って行き来します。
放電時には、負極に蓄えられたリチウムイオンがプラスの電荷を持って正極へ移動し、電子が外部回路を通って流れることで電力が発生します。
充電時は、外部から電流を流すことで正極から負極へとリチウムイオンが戻り、再び使える状態になります。
リチウムイオンは液体や固体の中を動きやすい性質があるため、効率よく充放電できるのです。
軽量で大容量、自己放電が少ないという特性から、スマートフォン、ノートパソコン、電気自動車など幅広い用途で活躍しています。
電池を安全に使うための注意点
電池は便利な反面、使い方や保管方法を誤ると液漏れ、発熱、破裂といった危険を伴います。
特にアルカリ乾電池の液は強いアルカリ性の劇薬で、皮膚に触れると化学火傷、目に入ると失明の危険があります。
安全に電池を使うには、正しい保管場所の選び方や、使用時の注意点を知っておくことが欠かせません。
日頃から適切な扱い方を心がけることで、事故を防ぎ、電池を長持ちさせることができます。
電池の正しい保管方法
電池の保管には、温度と湿度の管理が欠かせません。
直射日光や高温多湿の場所は避け、10度から25度の涼しく乾燥した場所に保管してください。
炎天下の車内など極端な高温下に放置すると、液漏れや破裂の原因となります。
冷蔵庫での保管は、取り出した時に結露が発生してサビの原因になるためおすすめできません。
金属類と一緒に保管すると、プラス極とマイナス極がショートして発熱、液漏れ、破裂の危険があるため、ネックレスや鍵、コインなどとは分けて保管しましょう。
新しい電池と使いかけの電池は混在しないように分けて保管し、長期間使わない機器からは電池を取り出しておくことが大切です。
電池には使用推奨期限があるため、期限を確認して期限内に使い始めることをおすすめします。
使用時に守るべきこと
電池を使う際は、いくつかの基本ルールを守ることで安全性が高まります。
異なる種類の電池や、新旧の電池を混ぜて使わないでください。
電池の性能が違うため、発熱や液漏れの原因となります。
同じアルカリ乾電池でも、メーカーや銘柄が異なるものは混ぜないようにしましょう。
電池は高所から落とすなど強い衝撃を与えると、変形して液漏れや破裂に至る恐れがあります。
長く使用しない機器に電池を入れっぱなしにすると、過放電して液漏れを起こすため、早めに取り出して保管しましょう。
もし液漏れが発生した場合は、素手で触らず、ビニール手袋をして処理してください。
液が目に入った時はすぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けることが必要です。
参考サイト
https://www.baj.or.jp/battery/qa/mechanism.html
https://www.panasonic.com/jp/energy/study/academy/sikumi.html
https://panasonic.jp/battery/contents/guide/storage.html